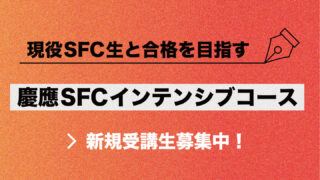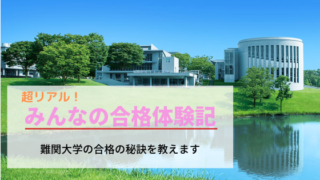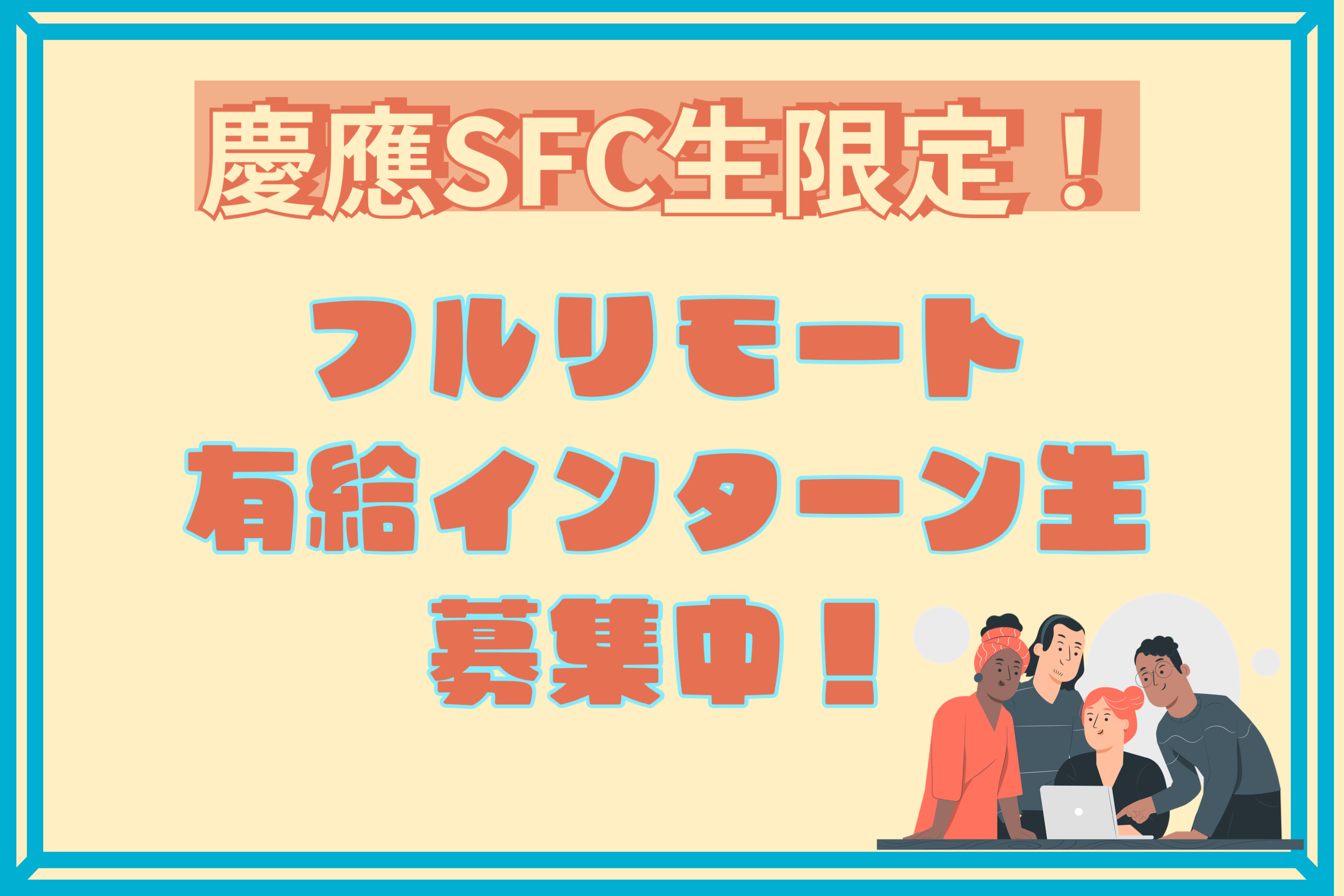この記事の目次
プロフィール・受験結果
出身校:茨城県立高校 – 偏差値68
部活:小学校から高校までバスケ部
志望時期:高校3年11月
使用科目:現代文,英語,情報,小論文
通塾:高3の12月 〜 :小論文のトリセツ “慶應SFC小論文の駆け込み寺”
受験結果
- 合格
- 一般英語: 慶應義塾大学 総合政策学部
- 共通テ3科: 中央大学 国際情報学部 (88%)
- 共通テ2科: 神田外語大学 グローバルリベラルアーツ学部 – 特待 (90%)
- 不合格
- 一般英語: 慶應義塾大学 環境情報学部
- 一般D方式: 青山学院大学 社会情報学部
- 共通テ3科: 中央大学 国際経営学部 (88%)
自己紹介
こんにちは、はるきです。
私は2025年に慶應義塾大学総合政策学部を一般選抜で合格しました。私は、高3の9月まで美大を志望していたため、慶應SFCを目指し始めたのは高3の11月ごろでした。そもそもSFCを知ったのも、美大受験を辞めると決めてからであったためSFC志望者の中でもすごく遅れをとっていたと思います。しかし、限られた時間の中でできることだけに集中して取り組むことで、結果的に効率よく学力がつきました。
慶應SFCを志望するまでの経緯
私は、もともと自然科学系の研究に興味がありました。高校1年生の時には、筑波大の高校生向けプロジェクトに参加し、高校2年生からは理数探求を行えるクラスに在籍して生物探求を行うなど、主に研究系の活動に取り組んでいました。その流れで、最初は国立理系志望でした。
しかし、自分の興味のある分野が多いが故にうまく絞れなかったので、あえて絞るのを辞めて分野的に遠い芸術的な学問に進もうと考えたもののうまくいきませんでした。このように自分がどの分野の学部、大学を受験するか悩んでいた時に、SFCを知りました。その後、実際にSFC万学博覧会でキャンパスの様子を見て、SFCを第一志望に決めました。
慶應SFC英語 対策の勉強法
SFC英語対策の使用参考書
- 英単語, 熟語
- システム英単語
- 速読英熟語
- SPARTA3
- リンガメタリカ
- 英語長文
- やっておきたい英語長文500
- ポラリス3
- でる!でた!中級
- レベル別英語長文5
- 英文法
- Bright Stage
- レベル別英文法5,6
- ポラリスファイナルステージ3
- 長文解釈
- 英文読解の透視図
- 慶應対策
- 赤本
- 世界一わかりやすい慶應の合格講座
基礎的もしくは網羅性のある参考書を各分野一冊ずつ決めてメインで使い続けていました。
メイン以外の教材や長文問題集などは2,3周くらいやった後、音読や飽きた時に眺めるのに使っていました。直前期はそれまでメインで使っていたものと志望校対策に特化した参考書を並行して取り組んでいました。具体的には、単語帳はシステム英単語、文法はBright Stage、長文解釈は英文読解の透視図をメインで使っていました。
SFCの英語は、多くの大学入試では目にしないような単語がたくさん出てきます。そのため、できるだけ多くの文章を読み幅広い分野の単語に触れる必要があります。私は、学校に置いてあった様々な大学の赤本に載っている長文問題を解いてみたりニュース記事を読んだりして、知らない内容の文章と単語に触れるようにしていました。また、過去問で出た知らない単語には印をつけて次解いた時に覚えていたか確認したり何度か見返したりしていました。
しかし、このようにできるだけ多くの単語をインプットしたとしても、本番の問題文中に知らない単語が一つも出ないなんてことは期待できません。そこで、単語力の穴を埋めるために高い文法力が必要になります。いくつか知らない単語があったとしても文法の知識がしっかりついていると、正確に文意を取ることができ単語の意味自体の予測もできます。私は、SFC対策を始めた当初は語彙力が不足していただけでなく文法の知識に抜けが多く、感覚的に英文を読んでいたため過去問を解いても5割程度でした。そこで、残り期間の少なさに変に焦ることなく、学校で配られていた英文法の基礎的な参考書(Bright Stage)を使って本番までに文法事項を総復習しようと決め、自分に足りなかった文法力をカバーしました。
難しい英単語は、日本語でも使わないような意味のものも多く、どうしても使う頻度の少なさゆえに忘れてしまいます。しかし、英文法の知識は理系科目でいう公式のようなものであるため身につけるまでにさほど時間がかかりません。よって、いくつもの単語を覚えることよりしっかりとした英文法の力を身につけて足りない語彙力の差を埋めることの方が、SFCの英語でより高い点数を取る近道になります。
また、SFCの英語は問題への取り組み方が非常に大事です。文章量が多い上に文章中が選択式の穴埋め問題になっているため、簡単に文章を理解することができず想像より時間がかかってしまい実力を出しきれないことがあります。
そこで、過去問演習の何回かは自分にあった解き方を見つけるために使うことをお勧めします。私は、”世界一わかりやすい慶應の合格講座”で紹介されていた、一つの問題文を3回読む方法を取り入れていました。1回目は話の大まかな流れを取れるようにさらっと読み、2回目は穴埋め問題を解きながら読み、3回目で最後の内容一致問題を解くという方法です。この解き方の利点は、話題自体が理解しづらい文章でも何度も読むことでだんだん話が見えてきて、内容理解と解答の進み方のバランスがとりやすいことです。一方で難点は、何度も文章を読むため時間の配分を間違えると最後の問題まで解ききれなくなってしまうことです。
私はこの解き方を採用した過去問演習が一番所要時間が短く、得点率が高かったため、それ以降の演習でも本番でもこの方法を使いました。これ以外にも解き方はたくさんあります。一番安定して点数が取れるような自分にあった解き方を見つけてみてください。
慶應SFC小論文 対策の勉強法
SFC小論文対策の使用参考書
- 小論文をひとつひとつわかりやすく
- 日本の論点
- 赤本
- 小論文のトリセツ「慶應SFC小論文の駆け込み寺」
私はSFCを目指し始めるまで入試小論文に触れたことがなかったため、まずは小論文の簡単な参考書を一冊だけ取り組み、入試小論文の基礎的な作法を身につけました。その後は赤本で対策をしようと考えていたのですが、学習の進め方が分からなかったため模索していたところ、小論文のトリセツの「SFC小論文の駆け込み寺」を見つけ、オンデマンドで受講しました。
SFC小論文の対策に関しては、「駆け込み寺」で教えてもらえたことだけで十分でした。オンデマンドで講座を受け、課題の過去問やニュースようやくなどにしっかりと取り組むことで必要な考え方が身につき、設問に対してどのように思考を進めて記述していけば良いかが明確になりました。
SFCの小論文は他学部、他大学の小論文試験とは大きく異なっています。基本的に一つの決まった答えが設定されていることはないので、対策として有効なのはSFCが好む考え方や視野を身につけておくことだと思います。また、対策において出題傾向、出題意図を捉えるのも難しいので、困ったら小論文のトリセツのようなSFC対策に特化している講座を受講することを強くお勧めします。
受験生へのメッセージ
SFCの一般受験の対策は、日本の大学の中では特殊に感じることが多いと思います。それは、SFC自体が他大学にはない魅力を持っているからだと入学した今、日々そう感じています。
そして、SFCの対策で一番有効なことは、「ひたすら自分の頭を使うこと」です。多くの人にとって受験対策は、知識の暗記が根幹にあります。しかし、SFCの対策は知識よりも思考や発想の力を身につけることが必要です。これは単に知識を身につけるよりも難易度が高いように思えますが、自分でアイデアを生み出す楽しさがあります。ぜひ、考えることを楽しみながらSFCの対策を進めてください。そうして気づいた時にはSFCが求めている学生像に近づいているはずです。


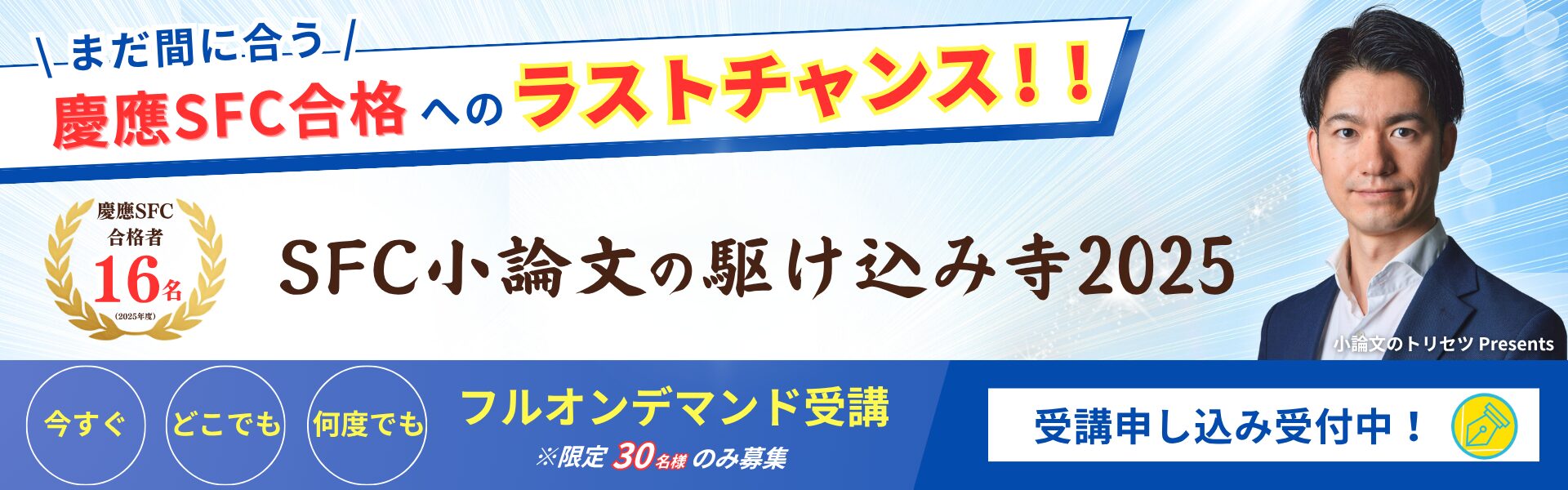

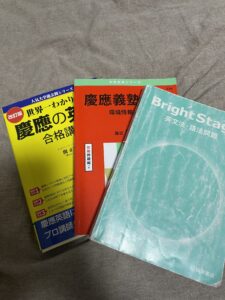


-320x180.png)