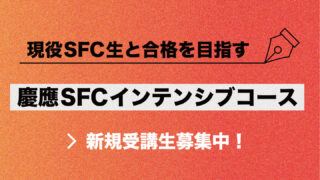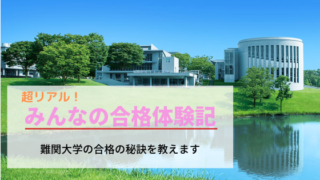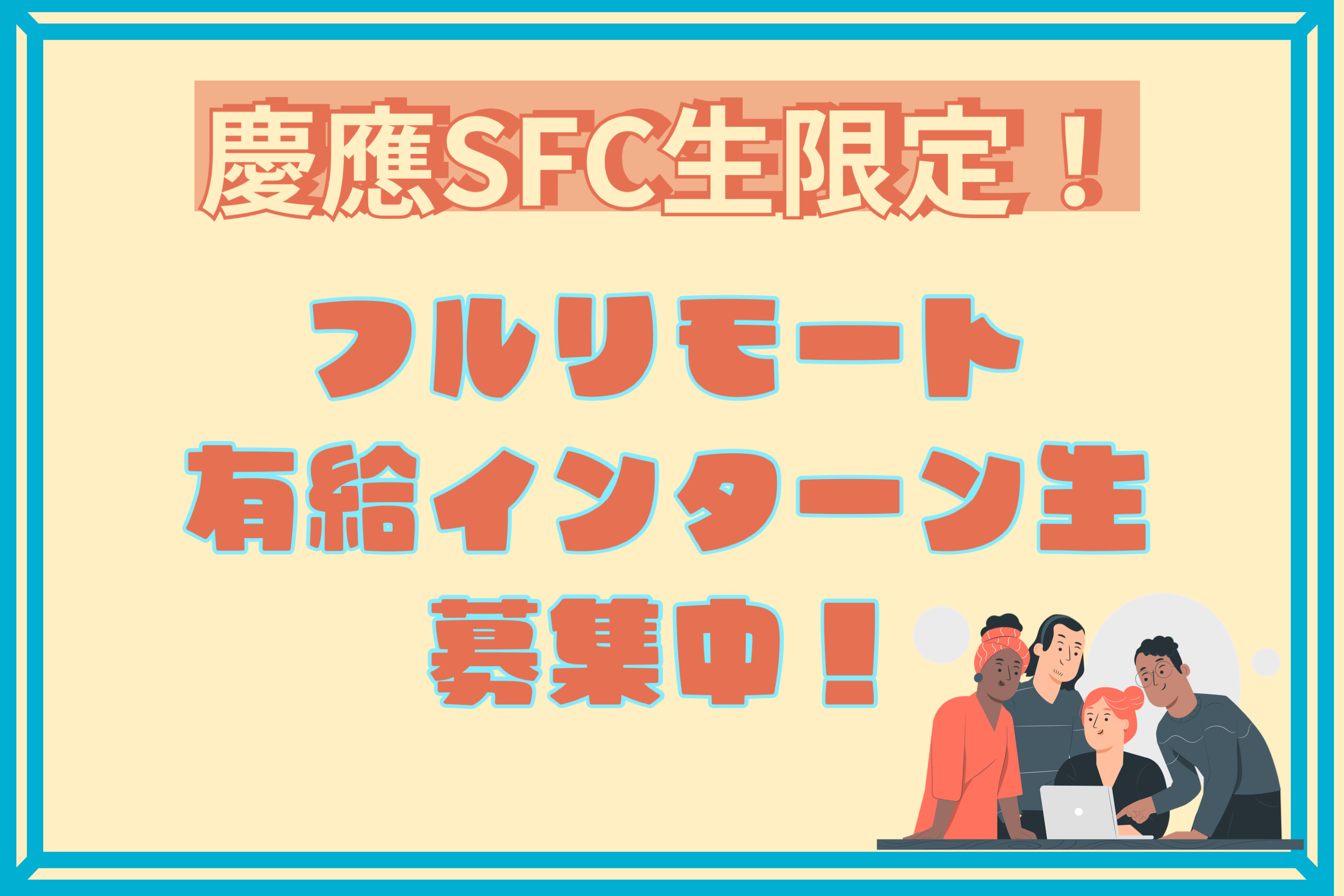この記事の目次
慶應義塾大学 総合政策学部2025年【問い】
問1: 「人間」とは何か、を議論せよ。
但し、「人間」の多義性(注1)、多面性(注2)にふれ、複数の人物の思想(注3)に言及すること。貴方が貴方に与えられた生きる時間を貴やして目指したい「人間」の在り様も併せて述べること。必要に応じて資料1から4も活用すること(注4)。
注1:ある言葉、表現が多くの意味を持つこと。言い換えれば、多様な定義が可能なこと。 注2:ある概念、存在が様々な側面を持つこと。言い換えれば、多様な議論が可能なこと。 注3:言及する人物に関しては「慶應義塾の創設者である福澤諭吉」や「慶應義塾大学総合政策学部の初代学部長である加藤寛」のように一定の紹介の上でその思想に触れること。 注4:これらの資料は過去の人物の思想の一部を記した文章であるが、これらの回答への採用は必須ではない。「人間」の多義性、多面性を例示する資料である。
問2: 「人間」は「未来社会」においてどう生きるべきかを議論せよ。
但し、資料5(注5)に表現された「未来社会」を批評(注6)したうえで、貴方の考える「未来社会」の特性に言及すること。必要に応じて資料6、資料7も活用し(注7)、未来社会の先導者(注8)たる貴方の立場で議論すること。
注5:資料5は絶対ではない。正確かどうかもわからない。あくまで思考の材料であり、乗り越えるべき最低限の水準である。良所は評価し、限界は指摘し、依拠しすぎないこと。 注6:批評とは、理由や根拠を示した上で、その作品の優劣を客観的に評価する事である。 注7:これらの資料は、地球規模での「未来社会」を予想した文章であるが、これらの回答への採用は必須ではない。発想と議論の幅を広げる材料である。また、これらもあくまで予想であり、このような未来となるかどうかも実際は分からない。 注8:慶應義塾の創立者は、資料8を「慶應義塾の目的」として書き残している。
問3: 「未来社会」において「人間」の先導者を目指す学生は、 SFCでどう時間を過ごすべきか、貴方の考えを教えてください。
但し、問1、問2での回答を踏まえた内容とすること。また、SFCには多様な学生が存在しえるため、貴方自身や、貴方自身に属する「学生」に限定してかまわない。実際にできるかどうかは考慮せず、こう過ごすべき、という主張でかまわない。
慶應義塾大学 総合政策学部2025年【答案例】
問1
人間の多義性と多面性について、複数の思想家の見解を整理しながら論じていく。エーリッヒ・フロムは、愛する能力を持つ存在として人間を捉え、その能力が社会によって形作られると指摘した。スマナサーラは「考える」という人間固有の特質に着目し、それが必ずしも幸せには結びつかないと説く。マルクス・アウレーリウスは、人生の無常性を説きながらも、自然の摂理に従うことで人は調和のとれた生を送れると主張した。シェイクスピアは人間存在の儚さを詠いながらも、その中に秘められた崇高さを見出している。
これらの多様な視点が示すように、人間は複数の側面を持つ存在である。技術革新が加速する現代において、人間の本質を問い直すことは重要な意味を持つ。なぜなら、人工知能やロボティクスの発展により、人間固有の特質が問われているからである。人間の本質を理解することは、未来社会を構想する上で不可欠な課題である。我々は各思想家の洞察を手がかりに、人間の多面的な姿を捉え直していく必要がある。(427文字)
問2
未来社会における人間の生き方について、提示された資料をもとに考察する。資料5と資料6は、2040年までの社会変容を予測している。そこでは、テクノロジーと社会の相互作用により、人々の生活様式が大きく変化することが示されている。特に、AIやロボティクスの進展、仮想空間の実用化、環境問題への対応が重要な課題として挙げられている。この変化の中で、人間はテクノロジーとの共生を模索しながら、自らの存在意義を問い直す必要がある。
資料7は、2075年に向けた経済予測を示している。世界経済の成長は鈍化するものの、新興国の台頭により、グローバルな富の再分配が進むとされる。しかし同時に、国内での格差拡大も予測されている。このような経済環境において、人間は単なる経済的価値の追求ではなく、持続可能な社会の構築に向けて行動する必要がある。資料1が指摘するように、現代社会における人間関係の商品化や、労働の疎外という問題に対して、批判的な視点を持ち続けることが重要である。
未来社会を生きる人間には、二つの重要な課題が突きつけられている。一つは、テクノロジーの発展がもたらす利便性を享受しながら、人間固有の価値を見失わないことである。資料2が示すように、人間の「考える力」を活かしつつ、過度な思考に囚われない均衡が求められる。もう一つは、グローバルな課題に対する責任ある行動である。資料6が示す5つのシナリオは、いずれも国際協調の重要性を指摘している。人間は、自己の利益追求を超えて、地球規模の問題解決に貢献する存在とならなければならない。このように、未来社会における人間は、テクノロジーとの調和を図りながら、より高次な社会的価値の実現に向けて行動することが求められているのである。(732文字)
問3
SFCにおいて「人間」の先導者となるために、以下の三つの観点から時間の過ごし方を提案する。第一に、新たな時代の夜明けを認識し、テクノロジーと人間性の調和を探求することである。問1で論じたように、人間は多面的な存在であり、その本質を理解することは未来社会を構想する上で不可欠である。SFCの学際的な環境を活かし、人文科学と自然科学の両面から「人間とは何か」という問いに向き合う必要がある。
第二に、未来社会が直面する課題に対して、具体的な解決策を模索することである。問2で検討したように、未来社会ではテクノロジーの進展により、人々の生活様式が大きく変化する。その中で、人間固有の価値を守りながら、いかに社会の発展に貢献できるかを考える。特に、SFCの特徴である実践的な学びを通じて、理論と実践の両面から課題解決にアプローチする。例えば、AIと人間の協働の在り方や、持続可能な社会の実現に向けた具体的な提案を行うプロジェクトに積極的に参加する。
第三に、多様な価値観を持つ学生との対話を通じて、未来社会における「人間」の可能性を探究することである。資料8が示すように、慶應義塾は「全社会の先導者たらんことを欲する」という理念を掲げている。この理念を実現するためには、個人の研鑽だけでなく、異なる背景を持つ学生との協働が不可欠である。SFCの国際的な環境を活かし、グローバルな視点から未来社会の課題を考察する。さらに、学生主体のプロジェクトを通じて、リーダーシップを実践的に学び、社会変革の担い手としての資質を磨く。このように、SFCでの時間を、未来社会における「人間」の在り方を探求し、実践する機会として最大限に活用するのである。(713文字)
慶應義塾大学 総合政策学部2025年【解説】
問1の解説
問題の本質を探る
今年度の問1は、「『人間』とは何か」という、一見すると哲学的で抽象的な問いかけのように見えます。しかし、この問題の真の狙いは、複数の思想家の見解を踏まえながら、現代社会における人間の在り方を考察する力を測ることにあります。
設問では制限字数は明記されていませんが、ある程度の字数(300〜800文字程度)の中で、「人間」の多義性や多面性に触れ、さらに受験生自身が目指す「人間」の在り方についても言及することが求められています。これは、単なる知識の暗記や資料の要約ではなく、多角的な視点から「人間」という概念を捉え直す力が問われているのです。
資料の読み解き方
提示された4つの資料は、それぞれ異なる時代、異なる立場から「人間」を論じています。エーリッヒ・フロムは現代資本主義社会における人間の愛する能力について、仏教者スマナサーラは人間の思考という特質について、ローマ皇帝マルクス・アウレーリウスは人生の無常性について、そして劇作家シェイクスピアは人間存在の儚さと崇高さについて語っています。
これらの資料を読む際に重要なのは、単に内容を理解するだけでなく、各思想家の主張の背景にある問題意識を把握することです。例えば、フロムの指摘する人間関係の商品化という問題は、現代のSNSやAIの発展によってより一層深刻になっているかもしれません。このように、過去の思想を現代的な文脈で捉え直す視点が求められています。
効果的な解答の組み立て方
論理的かつ説得力のある主張を展開するためには、アウトラインの作成段階で、段落構成を整理することが必要です。第一段落では、複数の思想家の見解を簡潔に整理しながら、「人間」という概念の多面性を示します。続く第二段落では、それらの視点を現代社会の文脈に位置づけ、自身が目指す「人間」の在り方について論じていきます。
特に重要なのは、単なる思想の羅列に終わらせないことです。例えば、フロムの愛する能力とスマナサーラの思考という特質は、どちらも現代社会において新たな課題に直面しています。このような思想間の関連性を見出し、現代的な意義を考察することで、より深みのある議論を展開することができます。
評価のポイントと対策
この問題では、資料の正確な理解、多様な視点の統合、独自の視点の提示、そして現代社会との関連付けが重要な評価基準となります。これらの力を養うためには、日頃から哲学書や新書を読み、現代社会の課題に関心を持つことが大切です。
また、数百文字程度の字数で回答作成することに慣れるためには、新聞の社説を要約する練習が効果的です。短い文章の中に複数の視点を盛り込み、なおかつ明確な主張を展開する技術は、継続的な訓練によって身につけることができます。
SFCの小論文試験では、単なる暗記や表面的な理解ではなく、深い思考力と創造的な発想が求められます。この問1もまた、従来の価値観が大きく変わりつつある現代において、「人間とは何か」を改めて問い直す機会となっています。
問2の解説
問題の本質を理解する
問2では「『人間』は『未来社会』においてどう生きるべきかを議論せよ」という問いが示されています。この問いは、単に未来社会の予測を述べることを求めているのではありません。むしろ、人間という存在が、急速に変化する社会の中でどのような価値観や生き方を持つべきかを、深く考察することを求めています。
本設問も字数制限はありませんが、700〜800文字以内を目安に作成しました。提示された資料、特に資料5(AIとの対話)、資料6(GLOBAL TRENDS 2040)、資料7(The Path to 2075)を踏まえながら、未来社会の特徴を分析し、そこでの人間の在り方を論じることが求められています。
資料の活用と分析の視点
未来社会の特徴を理解する上で、三つの重要な資料が提示されています。
まず、資料5では、テクノロジーと人間の共生という観点から未来社会が描かれています。AIの進化、量子コンピューティング、仮想現実など、新しい技術が人々の生活をどのように変えていくのかが具体的に示されています。
資料6の「GLOBAL TRENDS 2040」では、より政治的・社会的な視点から未来社会が分析されています。民主主義の変容、国際秩序の再編、気候変動問題など、グローバルな課題が提示されています。特に注目すべきは、五つの異なるシナリオを通じて、未来社会の不確実性と多様性が示されている点です。
さらに資料7では、2075年までの経済予測を通じて、人口動態の変化や経済成長の鈍化、格差の問題など、より長期的な視点からの分析が示されています。これらの資料は、未来社会が単一の方向に進むのではなく、様々な可能性と課題を含んでいることを教えてくれます。
効果的な解答の構築
この問題に対する優れた解答を作るためには、三つの要素を組み込むことが重要です。
第一に、未来社会の特徴を的確に把握し、その社会で人間が直面する課題を明確にすることです。テクノロジーの発展、環境問題、社会構造の変化など、複数の観点から課題を整理します。
第二に、それらの課題に対して人間がどのように向き合うべきかを、具体的に論じることです。例えば、AIと人間の協働の在り方、持続可能な社会の実現に向けた行動、グローバルな課題への取り組みなど、実践的な視点からの提案が求められます。
第三に、人間固有の価値や可能性を見出し、それを未来社会でどのように活かしていくかを論じることです。資料1から4で示された人間の本質に関する考察を踏まえながら、技術革新の時代における人間の存在意義を探求することが重要です。
より良い答案を目指して
この問題では、未来社会の予測と人間の在り方という二つの要素を有機的に結びつけることが求められます。そのためには、日頃から技術革新や社会変化に関する報道に関心を持ち、それらが人間の生活や価値観にどのような影響を与えるかを考察する習慣をつけることが大切です。
また、環境問題やAIの発展など、現代社会が直面している課題について、単なる問題の指摘にとどまらず、解決に向けた具体的な提案を考える訓練も有効です。慶應SFCの小論文では、創造的な思考力と実践的な提案力が重視されているのです。
問3の解説
問題の特徴と意図を読み解く
問3は「『未来社会』において『人間』の先導者を目指す学生は、SFCでどう時間を過ごすべきか、貴方の考えを教えてください」という問いかけです。この設問は、SFC受験において最も重要な意味を持つ問題だと言えるでしょう。なぜなら、受験生の問題意識とSFCの教育理念との整合性、そして具体的な学びのビジョンを問うているからです。
特に注目すべきは、問1、問2での回答を踏まえた上で論じることが求められている点です。つまり、「人間とは何か」という本質的な問いと、「未来社会でどう生きるべきか」という実践的な課題を結びつけながら、SFCでの具体的な学びを構想することが求められているのです。
求められる回答の要素
この問題で高い評価を得るためには、SFCの特徴を正確に理解し、それを自身の学びの構想と結びつけることが重要です。SFCの特徴として、文理融合の学び、プロジェクト型学習、国際性、そして最先端技術への取り組みが挙げられます。しかし、単にこれらの特徴を列挙するだけでは不十分です。
重要なのは、これらの特徴を活かして、どのように自身の問題意識を深め、実践的な力を養っていくのかを具体的に描くことです。例えば、情報技術と人文科学の知見を組み合わせて新しい社会システムを構想したり、地域社会と連携したプロジェクトを通じて実践的な問題解決能力を培ったりする具体的なビジョンが求められます。
効果的な論述の展開方法
本設問も、700〜800字程度を想定しており、3段落構成で論を展開しています。
第一段落では、SFCで学ぶ意義と目的を明確にします。ここでは、資料8に示された慶應義塾の理念「全社会の先導者たらんことを欲する」との関連を意識することが重要です。
第二段落では、具体的な学びの計画を提示します。例えば、デジタルテクノロジーと人間社会の関係を探究する研究会への参加、環境問題の解決に向けた国際プロジェクトの立ち上げ、AIと人間の共生をテーマとしたフィールドワークなど、具体的な活動イメージを示すことが求められます。
第三段落では、そうした学びを通じて得られる成果と、未来社会への貢献について論じます。ここでは、個人の成長にとどまらず、社会全体への影響や貢献を視野に入れた展望を示すことが重要です。
より説得力のある回答を目指して
この問題では、SFCについての表面的な知識ではなく、その教育理念と方法を深く理解した上で、自身の問題意識と結びつける力が問われています。そのためには、SFCの教育プログラムやプロジェクトについて具体的に調べ、自分なりの学びのビジョンを練ることが大切です。
また、未来社会の課題に対する自身の問題意識を明確にし、それをSFCの学びとどのように結びつけていくのかを具体的に構想することも重要です。単なる抽象的な理想論ではなく、実現可能な学びの計画を示すことで、より説得力のある回答を作ることができるでしょう。

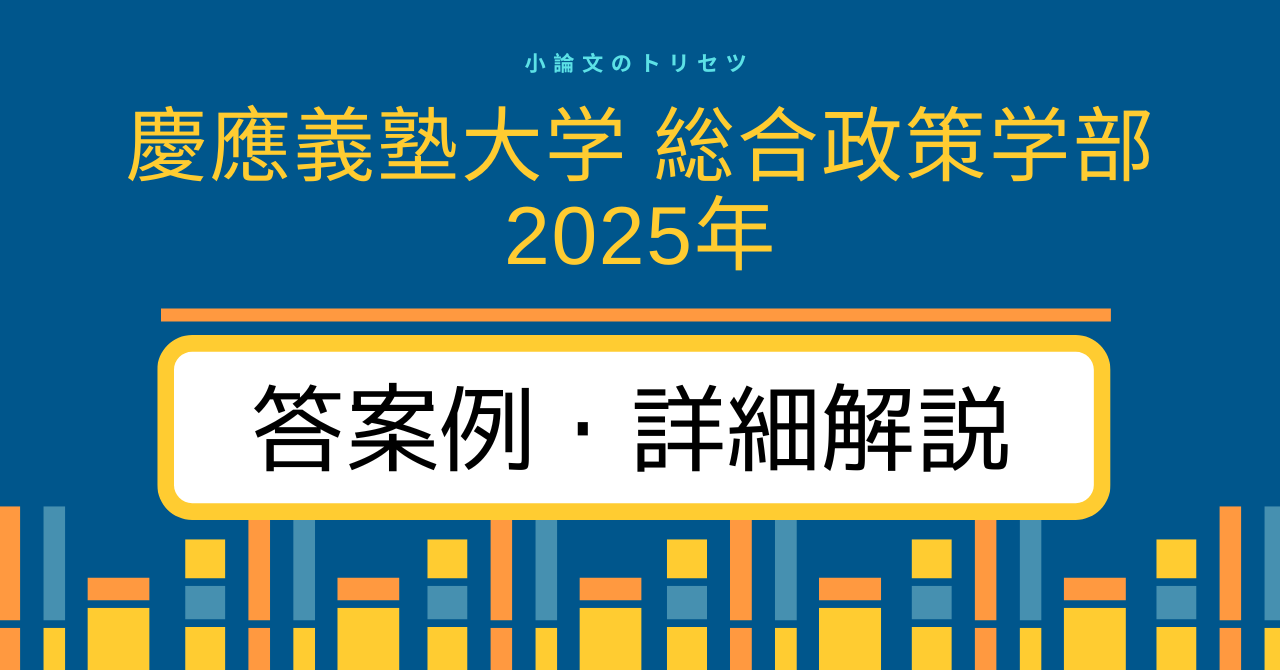
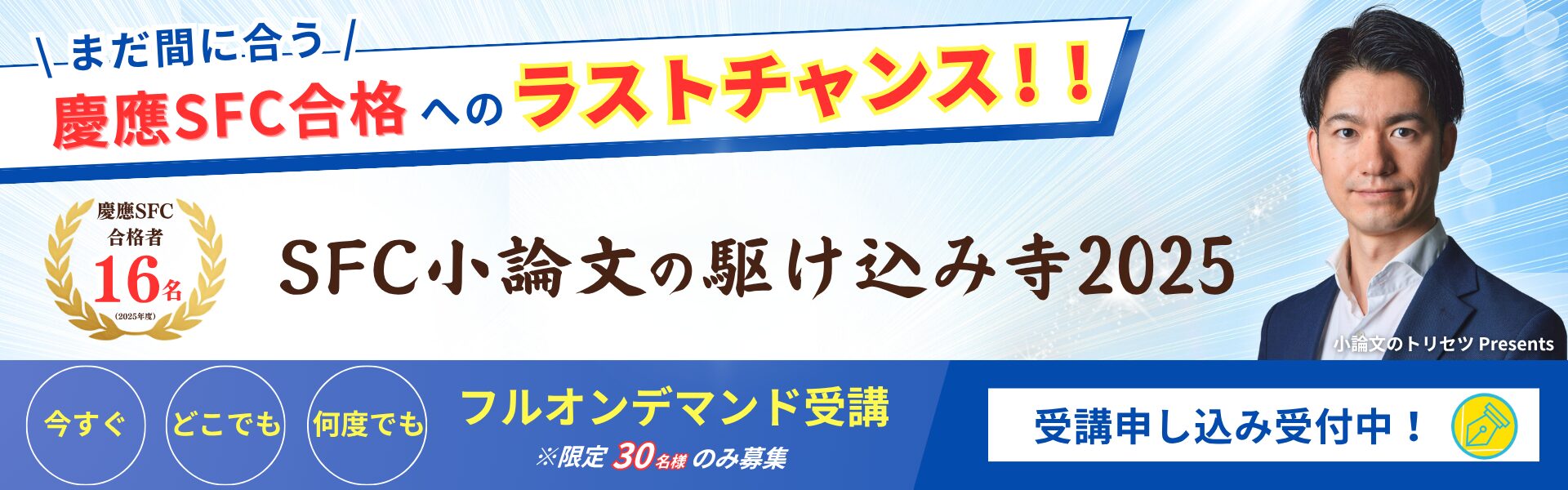

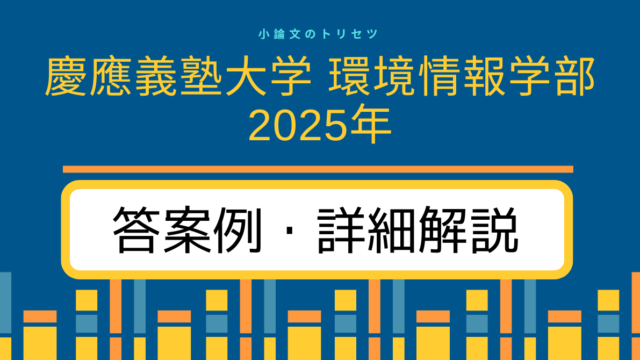



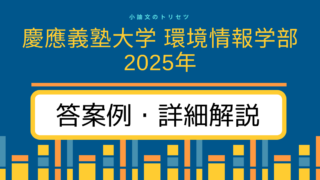
-320x180.png)