この記事の目次
慶應義塾大学 経済学部2017年【問い】
設問A
ソクラテス的論者とはどのように議論をする人なのか。課題文に基づき、200字以内で説明しなさい。
設問B
ソクラテス的なやり方で議論する能力を持つ人材は、組織(企業、行政機関など)において、どのような活躍ができるのか。また、そのためには、組織はどのような条件を備えることが必要か。課題文のみにとらわれず、あなたの考えを400字以内で論じなさい。
慶應義塾大学 経済学部2017年【答案例】
設問A 解答例
ソクラテス的論者とは、伝統や権威の規範を絶対化するのではなく、自分自身の考えを議論する人間である。規範や先入観を超えた側面(他者の他者性)に議論を通じて触れ、その側面を「異議」として唱えるのである。そして対話の際には、互いに絶対化した規範をぶつけ合うのではなくて、議論を通じて、妥協点や共通点を探ろうとするのである。また、近代の全体主義的な考えとは異なり、自分の考えや行動に責任を持つのである。(197字)
設問B 解答例
ソクラテス的論者は、議論を通じて、内面化した規範を超えた側面(他者の他者性)に触れる生き方を取る。これにより、自らの実存に基づいた経験の形成を可能にし、組織の規範を超えた側面を異議として唱え、規範に組み込んでゆくことで、組織の規範を拡大してゆくことができる。また、ソクラテス的論者はイノベーションを行うことができる。創造性は、他者との関係性、他者としての環境との関係性からしか生まれないからである。さらに、他者との議論を繰り返し行うことで、実存としての人間の共存を可能にする文化・社会の次元を拡大することができる。
このような生き方は、近代の官僚制的な組織では不可能である。では、どのような組織が必要か。それは、実存としての人間の共存を可能にする開かれた組織である。規範を絶対化するのではなく、規範を超えた側面を認め、ネットワークを通じて規範を拡大してゆくのだ。(380字)
慶應義塾大学 経済学部2017年【解説】
課題文の解説
まずは、課題文の読解について、最初から順を追って解説していこうと思う。
第一段落
一行目
『人間にとって、吟味されない人生は生きるに値しない』とソクラテスは公言していました。
「吟味されない人生」がテーマになりそうだ。ただ、この「吟味」の意味がまだわからない。次の文以降で吟味の意味を追っていくとしよう。
一行目
熱に浮かされた修辞を好み、議論に懐疑的であったデモクラシーの中で、彼はこうした批判的問いかけという理想への忠誠を貫いたために命を落としたのです。
「熱に浮かされた修辞」が分からない。しかし、次の「議論に懐疑的」からマイナスイメージだと推測できる。おそらく「中身のない綺麗事」というところだろうか。よって、「熱に浮かされた修辞を好み、議論に懐疑的なデモクラシー」というのは、「本質について考える事なく、表層的な言葉に踊らされる」、「異なる意見に耳を傾け、物事を深く多面的に考えるための議論を行わない」民主主義のあり方だと解釈できる。
そして、「彼はこうした批判的問いかけという理想への忠誠を貫いたために命を落としたのです」は、そういった議論を嫌う民主主義社会の中で、「吟味されない人生は生きるに値しない」という主張をしたため、反感を買い、殺されたということになる。
ここで、「吟味」の意味が分かりかけてくる。「議論を嫌い、物事を深く考えず、表層的な言葉に踊らされる社会」において反感を買うのだから、「吟味」というのは「表層的な言葉に踊らされず、物事を自分の頭で深く考え、多面的に捉える」といった趣旨だろう。
五行目
全ての学部生に哲学やその他の人文学の科目を一通り受けさせることが力説されてきたのは、そうした講義が、その内容及びその教育方法を通して、伝統や権威を盲信するのではなく、自分自身で考え議論する能力が、まさにソクラテスが言ったように、デモクラシーにとってかけがえのないものだと信じられているからです。
「伝統や権威を盲信するのではなく、自分自身で考え議論する能力」、これが「吟味」にあたるものであり、「伝統や権威を盲信すること」と「議論」が対比になっていることにも注目しておきたい。
また「伝統や権威を盲信しない」と言うのは、自己の内部で「自分の」意見を形成することである。様々な科目を学ばせる教育の狙いは、自己の内部に多様性を持たせ、特定の思想に囚われない知性を作るところにある。
第一段落まとめ
「伝統や権威を盲信する」、「他者との議論を行わない」。これは近代の官僚制的な組織のあり方そのものである。トップダウンなあり方である。
例えば、会社であれば、上司の言うことは絶対であり、部下からの口答えは一切許されない。ルール、規範は絶対。よってルールを超えた側面は、会社に認められず、創造性は抑圧される。ルールに従属した状態の個人ということで「従属主体化」と呼ばれる。
従属主体化した個人は、ルールというマニュアルに沿って、自らの意思に関係なく行動する。ルールを超えた側面を受け入れることはできない。
一方でソクラテスの主張する生き方は、実存(現実存在としての人間)の生き方である。実存とは、従属主体の対義語であり、「本来の人間のあり方」という意味で使われる。本来、人間は、何かの規範を絶対化して他者を受け付けないのではなく、他者と議論し、社会を作り上げ他者と共生するものである。
なので、第1段落は「従属主体」と「実存」の対比ということになる。
第二段落
十一行目
不決断というものは大抵、権威への服従と仲間の圧力によりさらに悪化するものです
「不決断」とは「決断しない」ということだが、どういう意味だろうか。第一段落が「従属主体」と「実存」の対比であったことを考えると、「従属主体が何かの決定を行う際に、自らの判断で決定するのではなく、絶対化された規範に基づいて自分の意思に関係なく決定する」から「不決断」なんだ、と捉えるのが自然であろう。
そして、「権威への服従」、「仲間の圧力」も官僚制的な組織の特徴である。「仲間の圧力」についてだが、官僚制的な組織においては、組織がトップダウンのピラミッド型になっており、自分の同僚も上司も、権威には絶対に歯向かわないため、自分も歯向かうわけにはいかないという意識が生まれる。よって、自分の意思に関係なく、「不決断」を行うことになる。
十四行目
対照的に、ソクラテスの批判的探求は完全に反権威主義的なものです。重要なのは話者の地位ではなく、ひたすら議論の中身なのです。
ソクラテスは、権威への服従(従属主体化)に反対する。対等な意見交換ができる社会を目指す。部下は上司の言うことを絶対に守らなければいけないと言う状況ではなく、部下の意見も、内容次第で受け入れ、規範に変化を加えたっていいじゃないか、「誰が言うかではなくて、何を言うかだ」、と言う主張である。ここでは「上司言うことだから絶対」というトップダウンのあり方ではなくて、上司と部下が対等な立場として議論を行うのである。
第三段落
十九行目
ソクラテス的論者は絶えず異議を唱える人です。各人の議論だけが物事をはっきりさせると知っているからです。あることを考えている人が多かろうが少なかろうが問題ではありません。数よりも議論に従うように訓練された人が、デモクラシーには有用なのです。
「ソクラテス的論者」とは、ソクラテスのように、権威に服従する従属主体的な生き方を嫌い、実存として他者と議論を行い、自分にない側面を受け入れるような論者なのだろう。なので「異議を唱える」という記述にも納得がいく。従属主体は、権威の規範を絶対化し、その規範に逆らうことはなく、その規範を超えた側面も受け入れない。ソクラテス的論者とは、その逆なので、一つの権威などを盲信することなく、官僚制的なヒエラルキーを意識せず、皆対等に議論すべきだと考える。これが「異議を唱える」につながるのである。
そして、民主主義社会においては、従属主体ではなく、実存としての人間が、絶えず議論を行い、異議として唱えられた新たな側面を規範に組み込み、規範をアップデートし続けることにより、「社会」がより良いものになるのではないか、という主張である。
第四段落
二十五行目
検証されない生活を送っている人々のさらなる問題は、しばしば互いに敬意を欠くことです。政治討論がスポーツの試合さながら自衛陣に得点をもたらすためのものだと考えられると、「相手陣営」は敵とみなされ、これを打ち負かしたい、辱めたいとすら願うようになるのです。妥協点や共通点を探ろうなどとは思いつきもしないのです。ホッケーの試合でシカゴ・ブラックホークスが敵チームとの「共通点」を探ったりしないのと同じです。
「検証されない生活」とは従属主体の生活のことだろう。自分の頭で考えることもなく、従属している規範に乗っ取られた状態で生活を送る。思考停止状態で、マニュアルに沿って動くだけである。
「互いに敬意を欠く」「妥協点や共通点を探ったりしない」とあり、スポーツの具体例が書かれている。要は、従属主体は議論ができないと言うことである。従属主体は、規範を超えた側面を受け入れることができない。自分の内面化している規範が絶対だと思い込んでいる。なので、自分とは異なる規範を内面化している他者に遭遇した時、互いがぶつかり合う。お互いに、自分の規範が絶対だと考え、相手の意見を聞こうとせず、最後まで対立する。だから、「打ち負かしたい」「辱めたい」と言う感情を持つようになるのだろう。
これにソクラテスは反対する。ソクラテスは、相手に敬意を持って、相手の話を聞く姿勢をとり、意見の共通点を探り、意見が合わないところは互いに妥協し、最終的に議論を合意に持って行き、実存の人間が共生できる社会の次元を拡大することを目標とするのである。
第五段落
三十四行目
さて今度は、この能力と、強力なグローバル市場に包囲されている現代の多元的なデモクラシーとの関連について考えてみましょう。
「現代の多元的デモクラシー」とは何か。ソクラテスの生きた時代は国家と言う大きな一つのデモクラシーしかなかったが、今日においては、国家性が解体し、グローバルな時代になり、様々なデモクラシーが存在していると言うことではないだろうか。
三十五行目
経済的成功がまさに目標とされる場合でも、一流の会社経営者たちは、批判的な声が沈黙させられないような企業文化を、つまり主体性と説明責任を重んじる文化を作り出す重要性を知悉しています。
「批判的な声が沈黙させられないような企業文化」とは、ソクラテス的論者の唱える「異議」を認める文化ということである。そして、「主体性と説明責任を重んじる文化」とは、内面化した権威の規範をマニュアルとして思考停止するのではなく、自らの意思で主体的に物事を決断し、その意思決定に関する責任を自らが持つ文化である。官僚制的な組織の場合、意思決定の根源は組織の規範にあるので、説明責任は個人ではなく組織が取る。
三十七行目
アメリカ合衆国で私が話す機会のあった優れたビジネス教育者たちは、私たちの最大の失敗のいくつか ―(具体例)― の原因として、イエスマンの文化を挙げていました。イエスマンの文化においては、権力と仲間の圧力がはびこり、批判的なアイデアは決して口にされないのです。
「イエスマンの文化」とは、官僚制のあり方そのものである。上に言われたことに、異議を唱えることなく、「イエス」と言う文化である。ここで言う「批判的なアイデア」とは、ソクラテス的論者の「異議」にあたる。
第七段落
六十二行目
そこでタゴールは、社会生活の官僚主義化と近代国家の情け容赦なく機械的な性質が、人々の道徳的想像力を鈍磨させ、その結果人々は何の良心の呵責もなくおぞましい事態を黙認するようになると強調しています。世界がまっしぐらに崩壊へ向かうのを避けたいなら独立した思考が重要である、とタゴールは言い添えています。
なぜ「おぞましい事態」が起きるのか。それは、官僚制の中の個人、いわば人間機械の中での部品である個人、は行動に責任を持たないからである。当事者意識がないから、平気で恐ろしいことができる。これに対し、ソクラテスは、当事者意識を持って、自らの判断で意思決定を行い、行動に責任を持つべきだと主張するのである。
設問Aの解説
ソクラテス的論者が「どのように議論する人」なのかを、課題文に基づいて説明させる問題。
課題文に書かれている「ソクラテスの議論」の記述を切り貼りしてつなげていくだけでは「説明」にはならない。様々な言い回しで記述される「ソクラテスの議論」の本質を理解し、意味をしっかりと考えてまとめていく必要がある。
ソクラテスの考えとはどのようなものであっただろうか。まず「反権威主義的」である。伝統や権威の規範を盲信して従属主体化するのではなく、実存の人間として、他者との議論を通じて、規範を超えた側面にふれ、その側面を受け入れ、物事を深く多面的に考え、自己の理性を拡大するというもの。次に「異議を唱える」ということ。ソクラテス的論者は、従属主体とは異なり、他者との対等な議論が可能である。相手に対して、敬意を払い、話を聞く姿勢を取る。互い持つ異なる規範をぶつけ合うのではなく、共通点や妥協点を探ろうと試みる。このような議論から、組織等の規範にない側面を自己の中に取り入れ、その側面を組織に対して、規範に対する「異議」として唱える。そして最後に「責任を持つ」ということ。近代の官僚制的な組織のあり方ではなく、自分の意思に基づいて意思決定を行い、当事者として行動に責任を持つ、というものであった。
これらを200字でまとめなければいけない。題意をみたすためには「どのように議論する人なのか」を記述しなければならない。ただ、「議論の仕方」の部分だけを書いても、かなり字数が余る。なので、「議論の仕方」を中心に、「なぜ議論が必要か」といった部分も加えて書く必要がある。
設問Bの解説
ソクラテス的論者が組織においてどう活躍できるか、またそのためには組織がどのような条件を備えることが必要かを論じる問題。
まずソクラテス的論者が組織に与える影響について考える。それはやはり「異議を唱える」という点だろう。異議を唱えることが組織にどのような影響を与えるのだろうか。
ソクラテスは、近代の官僚制的な組織のあり方を否定する形で「異議を唱える」という手段を取っている。では、官僚制的な組織の何が問題なのであろうか。それは「規範が拡大しない」ということである。官僚制的な組織の中では、各個人が「イエスマン」として働き、組織の規範を絶対化して、規範を超えた側面(他者の他者性)を認めない。これにより、既存の規範には、新しい側面が組み込まれず、ずっと凝り固まったままである。
このような組織は何か問題が起こっても、軌道修正することができない。これがエンロンのような失敗を導くことになるのである。組織は、絶えず新たな側面を規範に組み込み、規範をより良いものに変え続けなければならないのである。そのために、ソクラテスは異議を唱えるのである。他者との議論を通じて、規範を超えた側面を自己規範に組み込み、それを組織に対して異議として唱える。この異議を規範に組み込み続けることで、組織はより柔軟性のあるネットワークとして機能するようになるのである。柔軟性があれば、時代の変化に乗り遅れることもなくなるだろう。また「異議」が組織に対するイノベーションとなりうることもあるのである。官僚制的な組織では創造性は抑圧されてしまう。
このようなソクラテス的なあり方を実現するためには、組織がソクラテス的論者の「異議」を認めていくことが条件となる。「閉じた」変化のない組織ではなく、「開かれた」組織であり続ける必要があるのである。では、どのようにしてそのような組織を実現するか。それは、イエスマンが評価されない仕組みを作り上げることである。組織内部の個人の評価基準を多様化させたりすることが求められる。


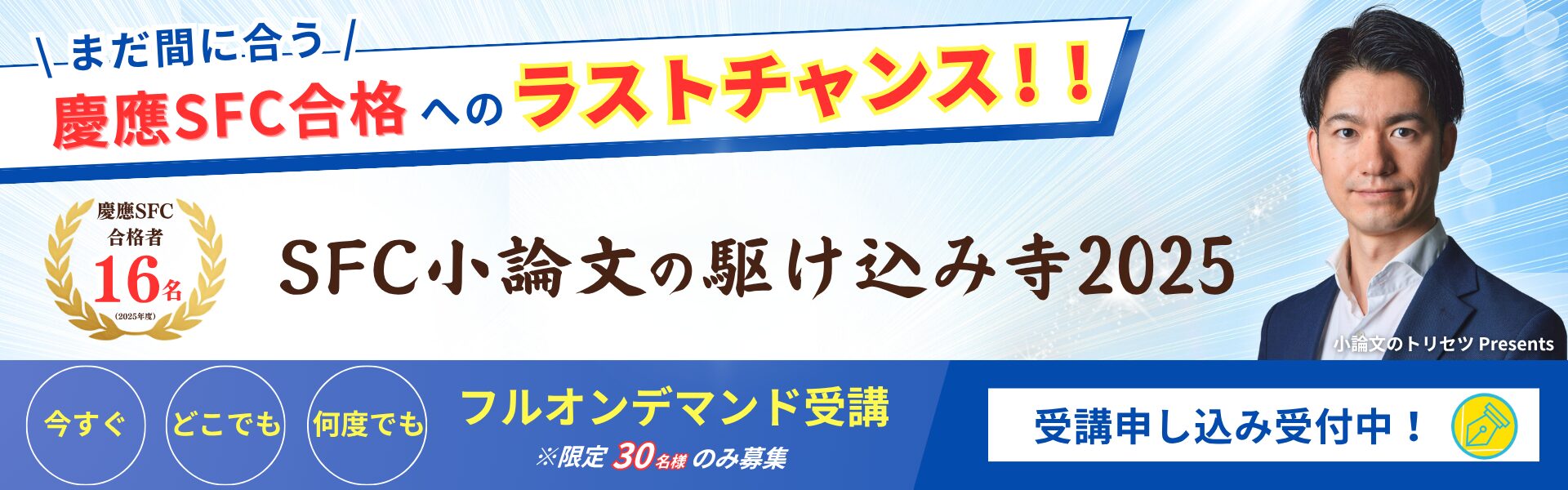







-320x180.png)







